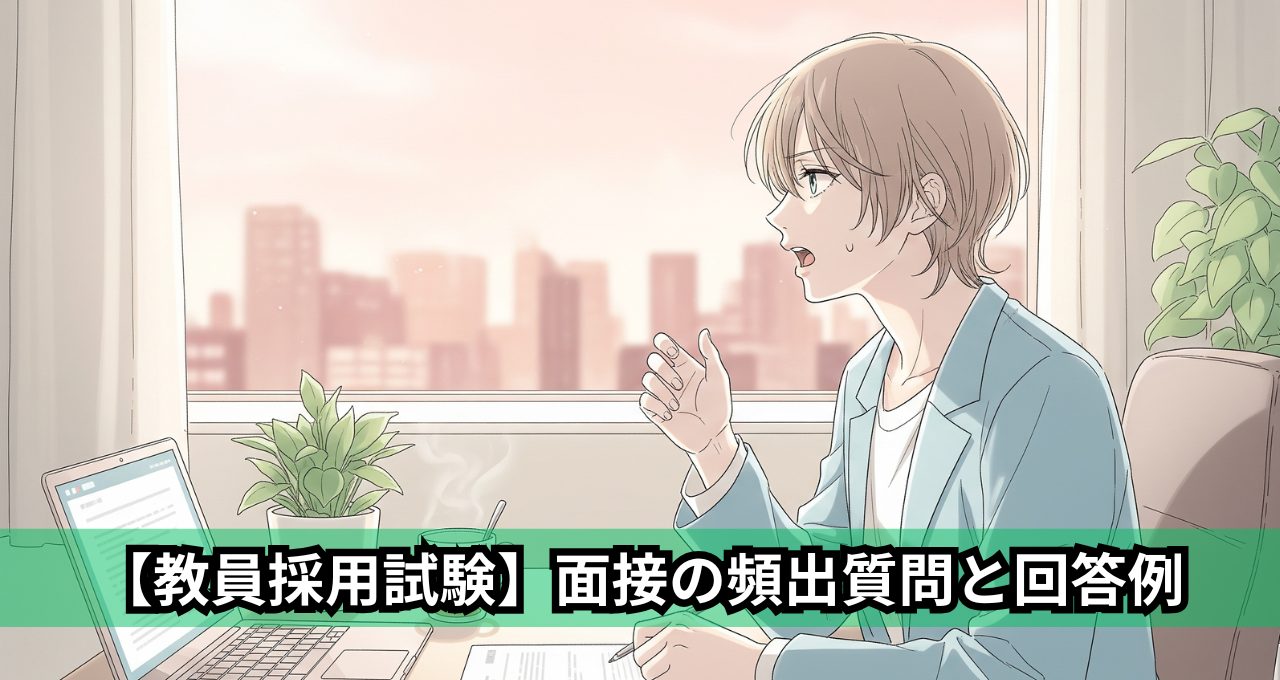- 「教員採用試験の面接で、いったい何を聞かれるんだろう…」
- 「この質問には、どう答えるのが正解なんだろう?」
教員採用試験の面接対策を始めると、次から次へと不安が湧いてきますよね。
そこで本記事では、全国の教員採用試験で実際に問われた過去問の中から、頻出の質問30個を厳選しました。
もちろん単なる質問リストではありません。一つひとつの質問に対して、
- 「なぜ、面接官はこの質問をするのか?(質問の意図)」
- 「どう答えれば、評価されるのか?(回答のポイント)」
を、具体的な回答例も交えながら徹底的に解説していきます。
この記事を最後まで読み込めば、面接への漠然とした不安は「こう答えよう!」という具体的な自信に変わりますよ。さあ、一緒に万全の準備を始めましょう。
▼面接試験の概要や対策方法は以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
はじめに:面接対策で最も大切なこと
本格的な質問解説に入る前に、一つだけ、非常に重要な心構えをお伝えします。
それは、この記事は「丸暗記するための模範解答集」ではない、ということです。
なぜなら、面接官が本当に知りたいのは、スラスラとよどみなく話される完璧な回答ではなく、あなた自身の言葉で語られる、あなただけの経験や考え方だからです。
どんなに素晴らしい回答例も、あなたの言葉でなければ面接官の心には響きません。
そこで、これから紹介する30個の質問と向き合う上で、常に意識してほしい「高評価を得る回答の3原則」があります。
- ①質問の意図を考える
-
「なぜ、この質問をされているんだろう?」と一歩立ち止まって考えてみましょう。意図がわかれば、答えるべきポイントが自然と見えてきます。
- ②自分の経験と結びつける
-
「私の強みは〇〇です」と主張するだけでなく、「△△という経験で、〇〇という力を発揮しました」というように、必ず具体的なエピソードで裏付けましょう。
- ③結論から簡潔に話す
-
「私の考えは〇〇です。なぜなら…」というように、必ず結論から話す「結論ファースト」を徹底してください。話が分かりやすくなり、論理的な思考力をアピールできます。
この3つの原則を意識して、これから解説する質問に回答を作成してみましょう!
自己PR・志望動機に関する質問
面接の冒頭で聞かれることが最も多い、最重要カテゴリーです。
ここで面接官に良い第一印象を与え、あなたという人間に興味を持ってもらえるかが、その後の展開を大きく左右します。
あなたという人間の「軸」となる部分、つまり「なぜ教員なのか」「なぜうちの自治体なのか」という、根本的な熱意と覚悟を見ています。自己分析がしっかりできているか、教員という仕事への理解度はどれくらいか、といった点も厳しくチェックされています。
どの質問にも共通して言えるのは、「結論ファースト」で話し始め、必ず「具体的なエピソード」で裏付けること。
あなたの言葉に説得力とオリジナリティが生まれます。
質問1:自己PRを1分でお願いします。
この質問は、あなたの「要約力」「自己分析力」「教員としてのポテンシャル」を同時に見ています。
限られた時間で最大限の効果を発揮するため、以下の3点を徹底しましょう。
- 時間を計って練習する:「1分」は意外と短いです。必ずストップウォッチで計り、体に染み込ませましょう。
- PREP法を意識する:
結論(強み)→ 理由・エピソード → 貢献(どう活かすか)の型で話すと、論理的で非常に伝わりやすくなります。 - 強みは1つか2つに絞る:あれもこれもと詰め込むと、結局何も印象に残りません。最もアピールしたい強みに絞り、具体的に深掘りしましょう。
NG回答例
→なぜNGなのか?
具体性がなく、あなたの「人柄」が全く伝わらないからです。「コミュニケーション能力」という言葉は便利ですが、あまりに多くの人が使うため、具体的なエピソードがないと面接官の印象に残りません。
→なぜNGなのか?
素晴らしい経験ですが、「その粘り強さを、教員としてどう活かせるのか」という最も重要な視点が欠けているからです。自己満足のエピソードで終わらせず、必ず教員の仕事に結びつける必要があります。
OK回答例
 福永
福永「自己PR」は、あなたの面接の第一印象を決める最重要の質問です。完璧に準備して、最高のスタートダッシュを切りましょう!
質問2:あなたの長所を教えてください。
自己PRと似ていますが、より端的にあなたの「強み」そのものに焦点を当てた質問です。
面接官は、あなたの長所が「教員の仕事にどう活かせるか」という視点で聞いています。
単に性格を述べるだけでなく、教育現場で再現性のある強みであることを示す必要があります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
あまりに抽象的で、他の受験生との差別化ができません。「明るく元気」が、具体的にどのような場面で、どのように子どもたちの成長に繋がるのかが不明瞭です。
OK回答例



「長所」+「それを裏付ける具体的なエピソード」+「教員としてどう活かすか」は、常にワンセットで考えましょう!
質問3:あなたの短所を教えてください。
この質問は、あなたを落とすための意地悪な質問ではありません。
面接官は、あなたが「自分を客観的に分析できているか(自己分析力)」、「自分の弱さと向き合い、改善しようと努力しているか(誠実さ・成長意欲)」を見ています。
NG回答例
→なぜNGなのか?
自己分析ができていない、あるいは傲慢な人物だと判断されてしまいます。完璧な人間はいません。自分を客観視できていないと思われるのは致命的です。
→なぜNGなのか?
教員として致命的・不適切な短所(時間を守れない、子どもが嫌い、感情の起伏が激しいなど)を正直に言いすぎるのはNGです。社会人としての資質を疑われてしまいます。
OK回答例



「短所」+「それが原因で起きた失敗談」+「改善するための具体的な努力」をセットで語ることで、誠実さと成長意欲をアピールするチャンスに変えましょう!
質問4:学生時代に最も力を入れたことは何ですか?
いわゆる「ガクチカ」です。
面接官は、あなたが「何に情熱を注ぐ人間なのか」という価値観や、「困難な課題にどう向き合うのか」という行動特性を知ろうとしています。
結果の凄さよりも、そこに至るまでの「過程」で、あなたが何を考え、どう行動したかが重要です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
事実を述べただけで、あなたがその経験から何を学び、どう成長したのかが全く伝わりません。面接官が知りたいのは「経験の概要」ではなく「あなたの学び」です。
OK回答例



「課題」→「自分の行動」→「結果」→「得た学び」のストーリーで語るのが王道です!
質問5:あなたの特技や趣味は何ですか?
面接の緊張をほぐすためのアイスブレイク的な質問ですが、油断は禁物です。
面接官は、あなたの「人柄」や「ストレス対処能力」、そして「学校現場で活かせる可能性」を探っています。あなたという人間を豊かに見せるチャンスと捉えましょう。
NG回答例
→なぜNGなのか?
無趣味な人間だと思われ、会話がそこで終わってしまいます。「この人は面白い人なのかな?」という面接官の興味を削いでしまう、非常にもったいない回答です。
OK回答例



もし可能であれば、部活動の指導や、子どもたちの興味関心を広げることに繋がりそうな趣味・特技を話せると、より高評価に繋がります!
質問6:なぜ、多くの職業の中から「教員」を志望するのですか?
志望動機の根幹を問う、最重要質問の一つです。
「子どもが好き」という気持ちだけでは不十分です。
面接官は、「なぜ塾講師や他の子どもと関わる仕事ではなく、『学校の教員』でなければならないのか」という、あなたの強い覚悟と教育への情熱を知りたがっています。
NG回答例
→なぜNGなのか?
多くの受験生が口にする言葉であり、具体性に欠けます。これだけでは、「それなら学童の先生でも良いのでは?」と思われてしまいます。「学校」という場で、「教員」として、でなければ実現できないことは何か、まで踏み込む必要があります。
OK回答例



あなただけの「原体験」を語ることが、他の受験生との絶対的な差別化に繋がります。なぜ、あなたは教員になりたいのですか?もう一度、深く掘り下げてみましょう。
質問7:なぜ、他の自治体ではなく、本県(市)を志望したのですか?
「地元だから」「実家から通えるから」という理由だけでは絶対に合格できません。
面接官は、「あなたは、うちの自治体の教育について、どれだけ本気で調べてきましたか?」という、志望度の高さと熱意を見ています。徹底した事前リサーチが不可欠です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
熱意が全く伝わりません。「愛着がある」のは素晴らしいことですが、それは「教員として貢献したい」という動機とは別です。どの自治体にも当てはまるような抽象的な理由ではなく、その自治体「でなければならない」理由を語る必要があります。
OK回答例



「自治体の教育施策」+「自分の強み・経験」=「私なら、こう貢献できます!」という方程式でアピールしましょう!
質問8:あなたの強みを、教員としてどう活かせますか?
「長所」や「自己PR」と似ていますが、より「現場での活用イメージ」に踏み込んだ質問です。
面接官は、あなたが自分の強みを客観視し、それを具体的な教育活動に落とし込んで考える力があるかを見ています。漠然とした精神論ではなく、具体的な行動レベルで語ることが重要です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
意気込みは伝わりますが、具体的に「何をするのか」が全く見えません。「忍耐力」を、どのような場面で、どのように発揮するのかを語らなければ、評価には繋がりません。
OK回答例



「私の強みは〇〇です。例えば、△△という場面で、□□という形で活かせます。」と、具体的な教育活動をイメージしながら話しましょう。
質問9:これまでの経験で、あなたの教育観に影響を与えたものはありますか?
あなたの教育哲学の「根っこ」を探る質問です。
面接官は、あなたがどのような経験を通して、どのような教師になりたいと考えるようになったのか、その人となりや価値観の背景を知りたがっています。
机上の空論ではない、あなた自身の体験から生まれた「生きた言葉」で語ることが求められます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
他人の言葉を借りただけで、あなた自身の考えが見えません。本や理論は素晴らしいものですが、それを「自分自身の経験」と結びつけて語らなければ、深みのある回答にはなりません。
OK回答例



あなたの人生の「ターニングポイント」を振り返ってみましょう。そこに、あなたの教育観の原石が眠っているはずです。
質問10:最後にアピールしたいことはありますか?
面接の締めくくりに与えられる、最後のチャンスです。
「特にありません」は絶対にNG。面接全体を通して伝えきれなかったことや、最も強調したい自分の熱意を、簡潔に、力強く伝えましょう。
面接官に「この人を採用したい」と思わせる、最後の一押しです。
NG回答例
→なぜNGなのか?
入職意欲が低い、あるいはアピールすることがない、と見なされてしまいます。絶好の機会を自ら放棄する、最もやってはいけない回答です。
→なぜNGなのか?
面接官はすでに聞いています。「また同じ話か」と思われ、応用力がない、あるいは話を聞いていない、という印象を与えかねません。
OK回答例



「本日の面接のお礼」+「自分の強みと熱意の再確認(要約)」+「採用後の抱負」で、感謝と意欲を伝えて締めくくりましょう!
教員としての資質・教育観に関する質問
このカテゴリーでは、あなたが「どんな教師になりたいのか」、そして具体的な指導場面で「どう行動できるのか」という、より実践的な資質を測られています。
あなたの教育に対する哲学や情熱の深さを確認すると同時に、生徒指導や保護者対応といった、学校現場で必ず直面するであろう課題への対応力を見ています。理想論だけでなく、具体的な行動レベルで語れるかが問われます。
「~を大切にします」という精神論で終わらせず、「なぜなら~だからです」「そのために、具体的に~します」という、根拠と具体策をセットで語ることが重要です。
可能であれば、文部科学省の学習指導要領や答申の内容に触れると、勉強熱心な姿勢もアピールできます。
質問1:あなたの理想の教師像を教えてください。
あなたの教育哲学の核となる部分を探る質問です。
有名な教育者の名前を挙げるだけでは評価されません。あなた自身の経験に基づいた、具体的な教師像を、あなた自身の言葉で語ることが求められます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
比喩表現で美しくはありますが、あまりに抽象的で、具体的に何をするのかが全く分かりません。あなたがどんな行動をとる教師なのか、面接官はイメージすることができません。
OK回答例



「どんな教師か(結論)」+「なぜそう思うか(経験)」+「そのためにどうするか(具体策)」の3点セットで語りましょう。
質問2:どのような学級(クラス)を作りたいですか?
あなたの学級経営観を問う質問です。
単に「楽しいクラス」といった雰囲気だけでなく、「学習面」と「生活面」の両方から、具体的なビジョンを持っているかどうかが評価のポイントになります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
理想としては素晴らしいですが、その「楽しさ」を実現するための具体的な手立てが述べられていません。また、学習規律やルールといった、学級経営の現実的な側面への視点が欠けていると判断される可能性があります。
OK回答例



「雰囲気(理想)」と「そのための具体策」はセットです。学習面と生活面、両方から語れると深みが出ます。
質問3:保護者からクレーム(厳しい意見)があった場合、どう対応しますか?
あなたの対人対応能力、特にストレス耐性と誠実さを見ています。
感情的にならず、組織の一員として冷静かつ適切に対応できるか、そのプロセスを具体的に説明できるかが重要です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
事実確認の前に全面的に謝罪してしまうと、学校側に非があることを認めたことになりかねません。誠意は大切ですが、手順を間違えると問題をこじらせる危険性があります。
→なぜNGなのか?
自分の正当性を主張するだけでは、保護者の感情を逆なでしてしまいます。まずは相手の話を聞く「傾聴」の姿勢が何よりも大切です。
OK回答例



「①傾聴→②事実確認→③報告・連絡・相談→④組織としての対応」この冷静なプロセスを語れるかが鍵です。
質問4:いじめを認知した場合、どのように対応しますか?
教員として避けては通れない、極めて重要な問題です。
いじめ問題に対する正しい知識(いじめ防止対策推進法など)と、組織の一員として迅速かつ適切に行動できるかという、具体的な対応手順を理解しているかが問われます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
加害者とされる児童への指導はもちろん必要ですが、それだけでは根本的な解決にはなりません。被害児童の心のケアや、他の児童への事実確認、保護者への連絡、管理職への報告など、やるべきことが抜け落ちています。
OK回答例



「即時報告」「被害者保護」「組織対応」がキーワード。絶対に一人で抱え込まないという姿勢が重要です。
質問5:特別な支援が必要な児童生徒に、どのように関わりますか?
インクルーシブ教育の理念が広まる中、全ての教員に求められる専門性を問う質問です。
特別な支援に関する正しい知識と、他の教員や専門家と連携する姿勢、そして何よりも、その子自身に寄り添う温かい眼差しを持っているかが見られています。
NG回答例
→なぜNGなのか?
一見、正しいように聞こえますが、「平等」と「公平」は異なります。その子の特性に応じた「合理的な配慮」を行わないことは、真の意味で平等とは言えません。個別最適な支援の視点が欠けていると判断されます。
OK回答例



「①正しい理解 ②専門家との連携 ③学級全体への働きかけ ④個別の合理的配慮」という、多層的な支援の視点を示しましょう。
質問6:ルールを守れない児童生徒に、どう指導しますか?
あなたの生徒指導観を具体的に問う質問です。
感情的に叱るのではなく、教育的な意図を持って、子どもの成長に繋がる指導ができるかを見ています。一方的な指導ではなく、子ども自身に考えさせ、納得させるプロセスを重視する姿勢が評価されます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
高圧的な指導は、子どもの反発を招くだけで、真の理解には繋がりません。また、ルールを守れない「背景」に目を向けず、行動だけを問題視している点も、教員としての配慮に欠ける印象を与えます。
OK回答例



「行動の背景を探る → なぜダメなのかを考えさせる → 納得させる」という、子どもの内面に働きかける指導プロセスが重要です。
質問7:学力がなかなか向上しない児童生徒に、どう対応しますか?
学習指導における、あなたの引き出しの多さを問う質問です。
全ての子どもに同じ指導をするのではなく、個々の状況に合わせて、多様なアプローチができるかが見られています。「個別最適な学び」というキーワードを意識すると良いでしょう。
NG回答例
→なぜNGなのか?
熱心ではありますが、指導法が画一的です。授業でわからなかったことを、同じ方法で繰り返しても、またわからずに終わってしまう可能性が高いです。つまずきの原因を分析する視点が欠けています。
OK回答例



「原因分析」→「多様なアプローチ」→「個別最適な学び」の流れで、指導の引き出しの多さを見せつけましょう!
質問8:同僚の先生方と、どのように協力していきたいですか?
学校はチームで動く組織です。あなたの協調性やコミュニケーション能力を見ています。
「若手として教えてもらう」という受け身の姿勢だけでなく、「自分もチームの一員として貢献したい」という主体的な姿勢を示すことが大切です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
謙虚な姿勢は良いですが、受け身で意欲が低いと捉えられかねません。「学ぶ」だけでなく、自分からチームに「貢献できること」は何か、という視点が欠けています。
OK回答例



「報連相(基本姿勢)」+「謙虚に学ぶ姿勢」+「自分から貢献できること」の三段構えで、理想の若手像をアピールしましょう。
質問9:教師として、最も必要な力は何だと思いますか?
あなたの教育哲学や、教職という仕事への理解の深さを問う質問です。
「教科指導力」「生徒指導力」など様々な答えがありますが、なぜそれが最も重要だと考えるのか、あなた自身の経験や考えに基づいた説得力のある理由を語れるかがポイントです。
NG回答例
→なぜNGなのか?
愛情はもちろん大前提として重要ですが、それだけではプロフェッショナルとしての資質をアピールできません。精神論に終始せず、より具体的なスキルや能力について言及する必要があります。
OK回答例



「〇〇な力です(結論)」+「なぜなら~だからです(理由)」+「私自身も~したいです(自己PR)」の流れで、説得力を持たせましょう。
質問10:子どもたちの学習意欲を、どのように引き出しますか?
授業づくりの根幹に関わる質問です。あなたの指導観や、具体的な授業での工夫、引き出しの多さが見られています。
「主体的・対話的で深い学び」の視点を持って、子どもが「受け身」ではなく「主役」になる授業を構想できているかをアピールしましょう。
NG回答例
→なぜNGなのか?
具体的に「どのような」発問をするのか、「どのように」テンポを良くするのかが見えません。小手先のテクニックに終始しており、学習内容と子どもの実態に基づいた工夫の視点が欠けています。
OK回答例



「導入」「展開」「まとめ」という授業の流れに沿って、具体的な手立てを語ると、面接官もあなたの授業をイメージしやすくなります。
志望する自治体に関する質問
あなたの「本気度」が試される場所です。「地元だから」という理由だけでは絶対に通用しません。
面接官は、あなたが「数ある自治体の中から、なぜ、うちの自治体を選んだのか」という、強い意志と熱意を知りたがっています。その自治体の教育について、どれだけ深く、真剣に調べてきたかが、そのまま志望度の高さとして評価されます。
教育委員会のホームページ、総合教育大綱、学校教育指導方針の3つは、必ず事前に読み込んでおきましょう。
そして、ただ施策を褒めるだけでなく、その施策に対して、自分の強みや経験を活かして「どう貢献できるか」まで踏み込んで語ることが、他の受験生と差をつける最大の鍵です。
質問1:本県(市)の教育施策で、特に関心のあるものは何ですか?
自治体研究の成果を最も直接的にアピールできる質問です。
どの施策を選ぶか、そしてそれをどう自分の言葉で語るかで、あなたの関心の方向性や深さが分かります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
感想を述べているだけで、なぜ関心を持ったのか、その施策に自分がどう関わりたいのかという、最も重要な部分が欠けています。これでは、ホームページを少し見ただけ、という浅い理解度だと判断されてしまいます。
OK回答例



「施策の名称」+「関心を持った理由(自身の経験)」+「自分ならこう貢献できる」という流れで、熱意を伝えましょう。
質問2:本県(市)が示す「求める教師像」について、あなたはどう考えますか?
自治体が「どんな先生に来てほしいか」を明文化したものが「求める教師像」です。
これを理解しているかは、その自治体を志望する上での大前提。その上で、求める教師像のどの部分が、自分自身の強みや経験と合致するのかを具体的に示す必要があります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
意気込みを語っているだけで、具体的に何をするのかが全く分かりません。「求める教師像」を自分事として捉え、自分の言葉で語れていないため、他人事のような印象を与えてしまいます。
OK回答例



「求める教師像」の中から、最も自分と重なる項目を1つ選び、それを裏付けるエピソードを語るのが王道です。
質問3:本県(市)の教育課題は何だと思いますか?また、どう貢献したいですか?
自治体の現状を、当事者意識を持って分析できているかを問う質問です。
ただ批判的な視点で課題を挙げるだけでなく、その課題解決に向けて、自分なら何ができるかという建設的な提案まで求められています。情報収集力と問題解決能力が試されます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
データに基づかない、一般論に終始しています。また、「課題」を指摘しただけで、その解決に「自分がどう貢献したいか」という最も重要な視点が抜け落ちています。
OK回答例



「データに基づく課題認識」+「その解決に繋がる自分の強み・経験」+「具体的な貢献策」の3点セットで、あなたの問題解決能力を示しましょう。
質問4:本県(市)の学校で、どのような教育実践をしてみたいですか?
あなたの教育への情熱と、具体的な授業づくりのアイデアを問う質問です。
単なる思いつきではなく、その自治体の教育方針や、子どもたちの実態を踏まえた上で、実現可能なプランを語れるかがポイントになります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
教育用語を使っていますが、具体的に「何をするのか」が全く見えてきません。これでは、流行りの言葉を知っているだけで、自分の授業ビジョンを持っていない、と判断されてしまいます。
OK回答例



「自治体の方針」+「具体的な活動内容」+「自分の経験の活かし方」で、あなただけのオリジナルプランをプレゼンしましょう!
質問5:本県(市)の子どもたちの印象を教えてください。
アイスブレイク的な質問に見えますが、あなたがどれだけその地域に関心を持ち、観察しているかを見ています。
実際に学校ボランティアなどで子どもたちと触れ合った経験があれば、それを元に語るのが最も説得力があります。
NG回答例
→なぜNGなのか?
あまりに一般的で、どこの地域の子どもたちにも当てはまってしまいます。その地域の子どもたちと真剣に向き合おうという姿勢が感じられません。
OK回答例



具体的なエピソードを一つ挙げるだけで、印象は大きく変わります。ボランティア経験や、公開授業、地域のイベントに参加した経験などを話せるとベストです。
質問6:本県(市)の教育大綱を読みましたか?感想を教えてください。
「はい/いいえ」で終わらない、受験者のリサーチ力を試す直球の質問です。「読んでいません」は論外。
「読みました」と答えた上で、どの部分に共感し、自分ならどう実践に活かすかを述べられるかが重要です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
読んだことは伝わりますが、感想が抽象的すぎます。「どの部分を読んで、どう感じたのか」という、あなた自身の考えが見えてきません。
OK回答例



大綱の中から、最も共感するキーワードを一つ見つけ、それを自分の教育観と結びつけて語るのが効果的です。
質問7:(地域特有の取り組みを挙げて)〇〇という教育活動について知っていますか?
自治体研究の深さをピンポイントで試す変化球の質問です。知っていれば大きなアピールチャンス。
もし知らなくても、正直に認め、学ぶ姿勢を示すことでマイナス評価を避けることができます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
知ったかぶりは、その後の深掘り質問ですぐに見抜かれます。嘘をつくことは、教員として最もやってはいけない「不誠実な態度」と見なされ、一発で信頼を失います。
OK回答例



知らないことは恥ではありません。不誠実な態度こそがNG。正直に認め、学ぶ意欲を示すことが最善の策です。
質問8:本県(市)で教員として働くことの魅力は何だと思いますか?
志望動機を別の角度から問う質問です。
給与や福利厚生といった待遇面ではなく、あくまで「教育的な魅力」という観点から、その自治体で働くことのやりがいや素晴らしさを語ることが求められます。
NG回答例
→なぜNGなのか?
自分が「与えてもらう」ことばかりに焦点が当たっており、主体性に欠ける印象を与えます。「自分がどう貢献したいか」という視点がなく、受け身の姿勢だと判断されかねません。
OK回答例



その自治体の教育的な「強み」を挙げ、その強みの中で「自分も活躍したい、貢献したい」という意欲を示すことがポイントです。
質問9:本県(市)の教育の強みと弱みは何だと思いますか?
自治体への理解度を測ると同時に、あなたの分析力や思考の深さを問う、やや難易度の高い質問です。
「弱み」を指摘する際は、単なる批判で終わらせず、改善に向けた自分なりの提案をセットで述べることが鉄則です。
NG回答例
→なぜNGなのか?
データに基づいている点は良いですが、ただ事実を指摘しているだけで、なぜそれが弱みなのか、どう改善すべきかという分析や提案がありません。これでは評論家と同じで、当事者意識が欠けていると見なされます。
OK回答例



「弱み」は「今後の伸びしろ」と捉え、「強み」と「弱み」を関連付けながら、自分なりの改善策をポジティブに提案しましょう。
質問10:これから本県(市)の教育にどのように貢献していきたいですか?
あなたの熱意と覚悟を最後に問う、まとめの質問です。
これまでの質問でアピールしてきた自分の強みや経験を総動員し、「私を採用すれば、こんなメリットがありますよ」という、力強いプレゼンテーションで締めくくりましょう。
NG回答例
→なぜNGなのか?
意気込みは素晴らしいですが、具体的に「何をして」貢献するのかが見えません。抽象的な精神論ではなく、あなたの能力に基づいた、具体的な貢献イメージを語る必要があります。
OK回答例



「自分の強み」と「自治体の教育方針」を改めて結びつけ、採用後の活躍イメージを具体的に、自信を持って語りきりましょう!
【自治体別】個人面接の過去問と傾向はこちら
ここまで、全国の自治体で共通して聞かれる頻出質問を見てきました。
しかし、最終的な合格を掴むためには、これらの全体的な傾向に加え、あなたが受験する自治体独自の質問傾向や、過去にどのような質問がされたかを具体的に知っておくことが不可欠です。
以下のリンクから、あなたに必要なエリア・自治体の詳細な過去問対策記事をチェックして、万全の準備を整えましょう。
まとめ|面接試験の過去問題と模範回答は使い方が大事
今回は、教員採用試験における面接試験の過去問題をもとに質問の意図や回答例を解説しました。
30個の頻出質問と向き合う中で、「こんなことまで聞かれるのか」という新たな発見や、「この質問なら、あの経験が話せそうだ」という手応えがあったのではないでしょうか。
面接対策で最も大切なのは、「どんな質問が来ても、対応できる自分だけの引き出し」を、どれだけ多く準備できるかです。この記事で紹介した30個の質問は、その引き出しを作るための最高のトレーニング教材になります。
完璧な模範回答を覚える必要はありません。大切なのは、
- 質問の意図を理解すること
- 自分自身の経験と結びつけて語ること
この2つです。
さあ、今日からできる第一歩として、まずはこの記事の中から5つの質問を選び、「自分ならどう答えるか」をノートに書き出すことから始めてみませんか?
その小さな積み重ねが、本番での揺るぎない自信に繋がります。あなたの健闘を心から祈っています!
▼「自己PR・志望動機はこれでいいんだろうか・・・」「この回答で面接官は納得するだろうか・・・」このような悩みを解決できるオンライン相談室を開講しました!独りで不安な方はぜひご利用ください。