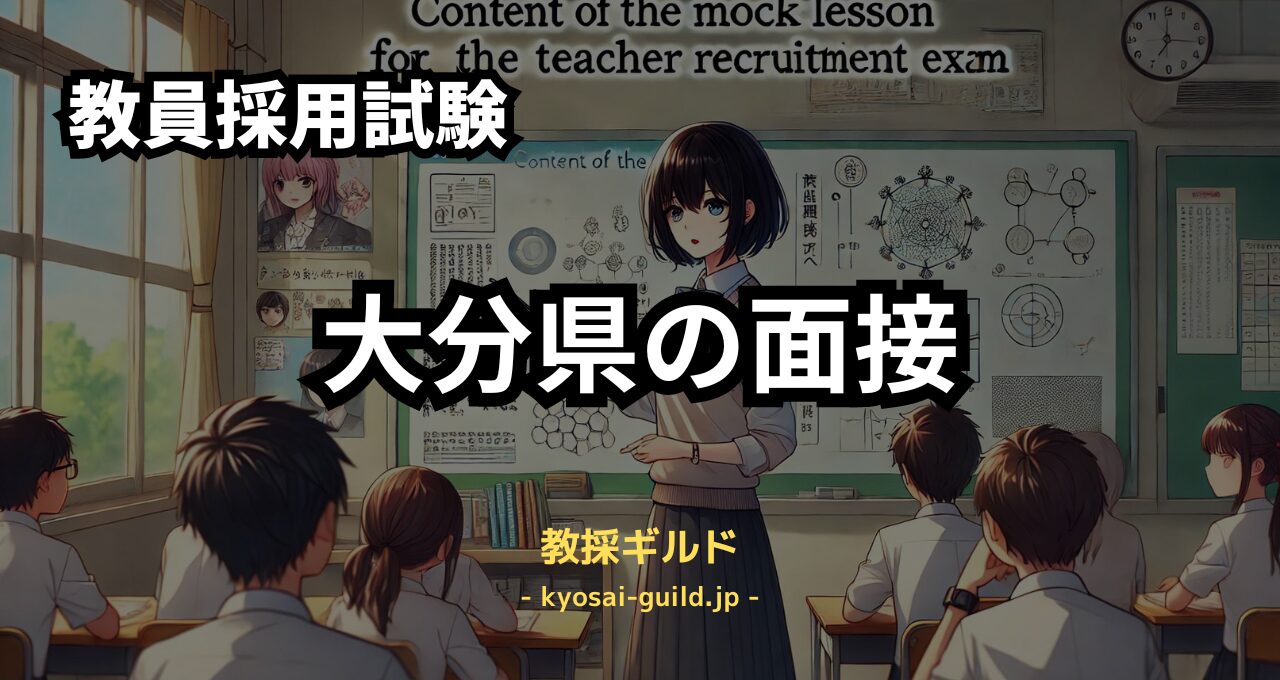「大分県の教採、筆記は通るけど面接が不安…」
「模擬授業って、何から手をつければいいの?」
そんな悩みを抱えていませんか?
近年、大分県教員採用試験は倍率が落ち着いており、筆記試験の通過は以前より現実的な目標になりました。しかし、それは同時に「人物評価」、つまり面接の重要性が格段に高まっていることを意味します。
付け焼き刃の対策では、面接官に見抜かれてしまいます。最終合格を確実にするには、いかに質の高い準備ができるかが合否を分けるのです。
この記事では、大分県教員採用試験の面接について、以下の点を徹底的に解説します。
- 面接の全体像と評価のポイント
- 合格レベルの模擬授業を構成する秘訣
- 面接官に響く自己紹介書の書き方と回答例
最後まで読めば、あなたが今すぐ何をすべきかが明確になり、自信を持って面接対策をスタートできますよ。一緒に頑張りましょう!
大分県教員採用試験の面接概要
まず、敵を知ることから始めましょう。大分県の面接は「個人面接Ⅰ」と「個人面接Ⅱ」の2段階で実施されるのが大きな特徴です。
それぞれの概要を下の表にまとめました。
| 試験内容 | 個人面接Ⅰ | 個人面接Ⅱ |
|---|---|---|
| 形式 | 模擬授業 or 場面指導(10分) + 口頭試問(10分) | 自己紹介書に基づく個人面接 |
| 試験時間 | 約20分 | 約20分 |
| 面接官 | 3人 | 3人 |
| 配点 | 270点~350点 ※校種により変動 | 350点 |
| 評価の観点 | ・指導力や専門性(学習指導要領の理解度) ・教育に対する情熱や使命感 ・倫理観、人間性 | |
※配点等は令和6年度(2024年実施)試験のものです。必ず最新の実施要項をご確認ください。
①個人面接Ⅰ(模擬授業・場面指導+口頭試問)
個人面接Ⅰは、あなたの「実践的指導力」を見る試験です。
- 模擬授業・場面指導(10分): 事前に公表されるテーマに基づき、目の前に子どもたちがいるかのように授業や指導を行います。
- 口頭試問(10分): 実施した模擬授業の内容について、面接官から質問を受けます。「なぜそのように指導したのか」という教育的意図を問われます。
②個人面接Ⅱ(自己紹介書に基づく面接)
個人面接Ⅱは、事前に提出する「自己紹介書」をもとに、あなたの「人物そのもの」を深く知るための試験です。
- 志望動機や自己PR
- 学生時代の経験
- 教育時事や不祥事に対する考え
など、幅広い質問を通して、あなたが大分県の教員としてふさわしい人物かどうかが総合的に判断されます。
特に大分県教育委員会が示す「大分県長期教育ビジョン」である「豊かな人間性と教育的愛情」「専門的な知識・技能」「社会人としての良識」を、あなたの言葉と経験でどう体現できるかをアピールすることが重要になりますね。
個人面接Ⅰ(模擬授業・場面指導)の攻略法
個人面接Ⅰ、特に最初の10分間で行われる「模擬授業」または「場面指導」は、二次試験の最大の山場と言っても過言ではありません。
ここでは、あなたの指導力、専門性、そして子どもたちへの情熱が試されます。しかし、ポイントさえ押さえれば、決して恐れることはありません。
模擬授業・場面指導の過去テーマ一覧
まずは、どのようなテーマが出題されるのかを知ることから始めましょう。大分県では、一次試験の合格発表と同時に、校種・教科ごとのテーマが公表されます。
以下に過去のテーマをまとめましたので、ご自身の受験する校種・教科の内容を確認し、どのような授業を組み立てるかイメージを膨らませてみてください。
2026(令和8)年度
| 校種・教科 | テーマ一覧 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 小中連携 | 理科 | 模擬授業(場面指導)のテーマ |
| 音楽 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 保体 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 英語 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 中学校 | 国語 | 模擬授業(場面指導)のテーマ |
| 社会 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 数学 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 理科 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 音楽 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 美術 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 保体 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 技術 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 家庭 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 英語 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 高等学校 | 国語 | 模擬授業(場面指導)のテーマ |
| 世界史 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 日本史 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 地理 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 公民 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 数学 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 物理 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 化学 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 生物 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 保体 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 音楽 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 美術 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 書道 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 英語 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 家庭 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 農業 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 機械 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 電気 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 建築 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 工化 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 商業 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 情報 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 福祉 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 特別支援 | 小学部 | 模擬授業(場面指導)のテーマ |
| 中学部 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 高等部 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 養護教諭 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
| 栄養教諭 | 模擬授業(場面指導)のテーマ | |
2025(令和7)年度
2024(令和6)年度
合格レベルの模擬授業を構成する3つのポイント
限られた10分間で面接官に「この先生の授業を受けてみたい!」と思わせるには、授業構成の工夫が不可欠です。以下の3つのポイントを意識して、授業案を練ってみましょう。
導入(最初の1分)で子どもの心を掴む
授業の成否は「最初の1分」で決まります。子ども役の面接官が、思わず授業に引き込まれるような「問いかけ」や「仕掛け」を準備しましょう。
単にテーマを告げるのではなく、身近な事象や意外な事実から入ることで、子どもたちの「知りたい!」という意欲を引き出すことができます。
展開(6〜7分)で「主体的・対話的な学び」を演出する
模擬授業は、あなたが一方的に説明するプレゼン大会ではありません。あくまでも主役は子どもたちです。
- 机間指導を必ず入れる: 「〇〇さん、良い意見だね」「そこのグループはどうかな?」など、実際に机の間を歩き、子どもたちに語りかける動きを入れましょう。これにより、個に応じた指導ができることをアピールできます。
- 子ども同士の対話を促す: 「今の〇〇さんの意見について、どう思いますか?」「ペアで1分間、考えを交換してみよう」といった発問で、子どもたちが対話する場面を意図的に作り出します。
- 板書は思考の足跡: 黒板(ホワイトボード)は、ただのメモ書きではありません。授業の流れが分かるように、色を使ったり、囲んだりして、思考のプロセスが可視化されるように工夫しましょう。事前に簡単な板書計画を立てておくと、当日慌てずに済みます。
まとめ(最後の2分)で「本時の学び」を実感させる
授業の最後には、「今日はこれができるようになった!」「これが分かった!」と、子どもたちが自分の成長を実感できるようなまとめをすることが大切です。
- 本時のねらいを再確認する: 「今日の授業で、皆さんは〇〇ができるようになりましたね」と、冒頭に示した学習目標(ねらい)が達成できたことを確認します。
- 短い言葉で振り返る: 子どもたちの言葉を使って、「〇〇さんの言う通り、〜ということが分かりましたね」とまとめることで、クラス全体で学びを共有した一体感を演出できます。
- 次への意欲につなげる: 「次は、この考えを使って、もっと難しい問題に挑戦してみよう!」など、次の学習への期待感を持たせる言葉で締めくくると、さらに良い印象を与えられます。
模擬授業後の口頭試問「頻出質問」と対策
模擬授業が終わると、すぐにその内容に関する口頭試問が始まります。
ここでの受け答えも評価の重要な一部です。定番の質問には、自信を持って答えられるように準備しておきましょう。
| 頻出質問 | 回答のポイント(面接官の意図) |
|---|---|
| 「今の授業を自己採点するなら何点ですか?また、その理由は?」 | 意図: 自己分析力・客観性を見たい。 対策: 高すぎず低すぎない点数(例: 70〜80点)を答えるのが無難。「子どもの主体性を引き出す導入はできたが、時間の関係で全員の意見を拾えなかったのが反省点です」など、できた点と改善点をセットで具体的に述べましょう。 |
| 「授業で一番工夫した点はどこですか?」 | 意図: 指導の核となる部分や教育的意図を知りたい。 対策: 「子どもたちが主体的に考える場面を設定した点です。特に、〇〇という発問で、子どもたちの思考を深めようと考えました」など、3つのポイントで挙げたような具体的な工夫と、その教育的ねらいを明確に説明します。 |
| 「この授業、この後の展開はどうしますか?」 | 意図: 計画性や長期的な視点があるかを見たい。 対策: 「本時の学びを定着させるために、次時は応用問題に取り組みます。また、〇〇が苦手な生徒には、別途補習プリントを用意することも考えています」など、単元全体の流れや、個に応じた指導計画まで言及できると高評価です。 |
| 「〇〇という意見の子がいたら、どう対応しますか?」 | 意図: 予期せぬ状況への対応力、児童生徒理解の深さを見たい。 対策: まず「素晴らしい意見ですね」と一旦受け止め、褒める姿勢が重要です。「その意見も尊重しつつ、『では、こういう見方はできないかな?』とクラス全体に問いかけ、多角的な視点を持たせたいです」など、決めつけずに思考を促す対応を示しましょう。 |
個人面接Ⅱ(自己紹介書)の対策
模擬授業であなたの「指導力」を示した後は、個人面接Ⅱで「人間性」や「教員としての資質」をアピールする番です。
この面接の土台となるのが、事前に提出する「自己紹介書」です。
面接官は自己紹介書を隅々まで読み込み、「この受験者はどんな人物だろう?」「もっと深く聞いてみたい」という質問を準備しています。
つまり、自己紹介書の完成度が、面接本番の流れを左右するのです。
面接官の心をつかむ「自己紹介書」の書き方
まずは、実際の自己紹介書を見てみましょう。

各項目をただ埋めるだけでは、その他大勢の受験生に埋もれてしまいます。あなたの魅力を最大限に伝えるためには、一貫したストーリーを意識することが重要です。
このように、「①あなたの強み」→「②それを裏付ける具体的なエピソード」→「③大分県の教育への貢献」という3点を線で結びつけることで、説得力のある自己PRが完成します。
特に③の部分では、大分県がどのような教育を目指しているかを理解し、自分の言葉で語れることが不可欠です。必ず「大分県長期教育ビジョン」に目を通し、あなたの考えと結びつけられる部分を探しておきましょう。
より具体的な書き方のテクニックや、面接官を惹きつけるポイントについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
頻出質問(過去問)から見る回答の準備
自己紹介書を提出したら、次はその内容に基づいた質疑応答の練習です。
以下に、過去によく聞かれた質問とその回答のポイントをまとめました。
なぜ、この質問をされるのか?(面接官の意図)を考えることが、的確な回答への近道です。
- 面接を受けるのは初めてですか。
- 緊張しやすいですか。
→いつもはどのように緊張をほぐしますか。 - 併願はしていますか。
→すべての試験に合格したらどこに行きますか。 - 志望動機を具体的に教えてください。
- 教員目指したのはいつ頃からですか。
- あなたの教員に向いていると長所は何ですか。
→その長所を教員としてどのように活かしますか。
→その長所を活かせた経験はありますか。 - これまでの経験で最も達成感があった出来事を教えてください。
- 教員として何を一番大切にしたいですか。
- 教員の不祥事についてどう思いますか。
→不祥事が起こる理由は何だと思いますか。 - これまでの人生で最も失敗したと思うことは何ですか。
→どうやった乗り越えましたか。 - 志望する校種・教科の魅力は何ですか。
→それを子供たちにどのように伝えますか。
これらの質問に対する自分なりの答えを準備し、何度も声に出して練習することが、自信につながります。
過去の質問項目や模範回答を以下の記事で詳しくまとめています。
面接対策はいつから始めるべき?
ここまで読んで、「面接対策って、やることがたくさんあるんだな…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
では、これらの対策は一体いつから始めるのがベストなのでしょうか。
結論から言うと、「筆記試験の勉強と並行して、できるだけ早く」始めることを強くおすすめします。理想を言えば、試験を受ける年の春、遅くとも夏が始まる前には着手したいところです。
「一次試験に受かるか分からないのに…」と思う気持ちも分かります。しかし、質の高い面接対策には、想像以上に時間がかかるものなのです。
- 自己分析(自分の強みや経験の棚卸し)には時間がかかる
- 大分県の教育施策や求める教師像を深く理解する必要がある
- 考えた回答を、自然に話せるように練習を重ねる必要がある
これらを、一次試験の合格発表後という短い期間で完璧に仕上げるのは、非常に困難です。
筆記の勉強の合間に、一日30分でも構いません。
「自分はどんな教員になりたいんだろう?」と考えたり、県の教育委員会のホームページを眺めたりするだけでも、立派な面接対策の一歩になります。
早期スタートが、あなたの自信と余裕を生み、他の受験生との大きな差になるのです。
具体的な対策方法は下記の記事でまとめています。
まとめ:自信を持って本番に臨むために
今回は、大分県教員採用試験の面接を突破するための具体的な対策について、詳しく解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
- 大分県の面接は「個人面接Ⅰ(模擬授業)」と「個人面接Ⅱ(人物面接)」の二本立て。
- 模擬授業は「導入・展開・まとめ」の構成と、「主体的・対話的」な演出が鍵。
- 自己紹介書は「強み・エピソード・県への貢献」を一貫したストーリーで語ることが重要。
- すべての回答の根底に「大分県の求める教師像」と「教育施策」への理解を置く。
- 面接対策は筆記と並行して早期に始めることで、圧倒的な差がつく。
面接試験は、あなたの教育にかける情熱や人間性を、自分の言葉で直接伝えられる絶好のチャンスです。この記事を参考に、まずは「自己分析」と「大分県の教育について調べる」ことから始めてみてください。
一つひとつ着実に準備を重ねていけば、本番では必ず自信を持って面接官と向き合えるはずです。
あなたの挑戦を心から応援しています!