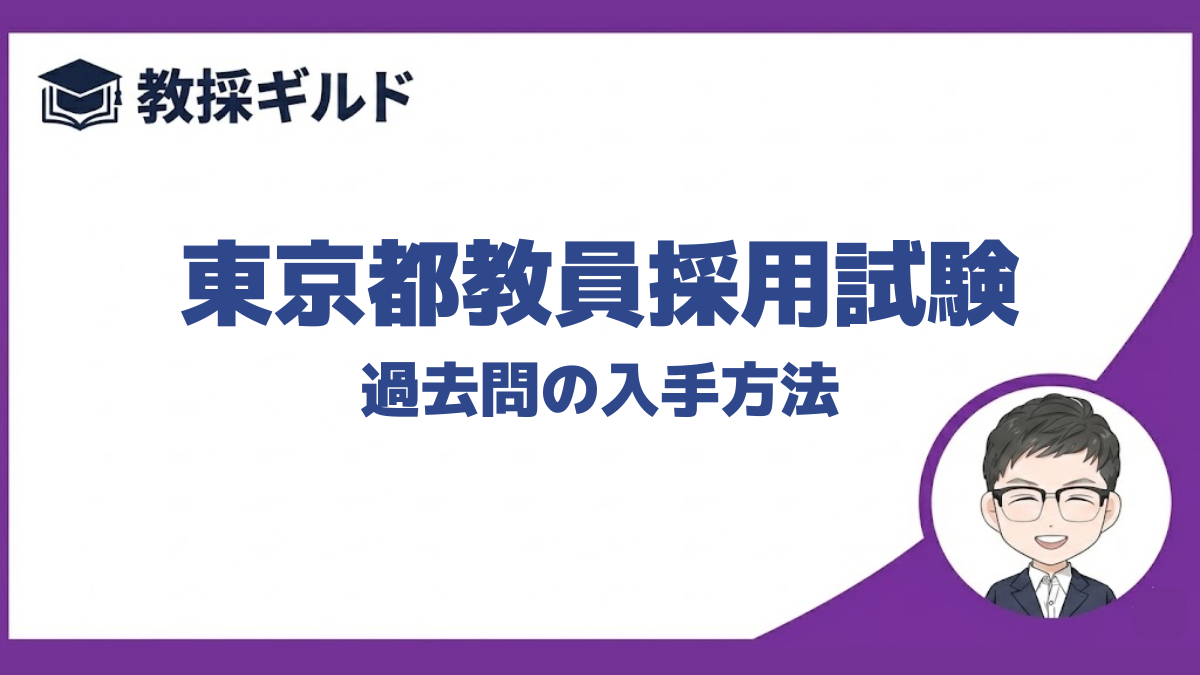この記事では、東京都教員採用試験の過去問を無料で入手できる方法と、効果的な活用法を紹介します。
記事で紹介する活用法を実践すれば、無駄な勉強を減らして効率的に合格ラインを超えられます。
ぜひ最後まで読んで、効率的な試験対策に役立ててください。
目次
東京都教員採用試験の過去問をダウンロード
東京都教員採用試験の過去問は、東京都教育委員会のホームページで無料公開されています。
教職教養と専門教養の両方がPDF形式でダウンロードできます。
以下から、直近5年分の過去問をチェックしてみましょう。
教職教養の問題・解答(過去5年分)
| 実施年度 (採用年度) | 教職教養 (PDF) |
|---|---|
| 2025 (令和8) | 問題・解答(PDF) |
| 2024 (令和7) | 問題・解答(PDF) |
| 2023 (令和6) | 問題・解答(PDF) |
| 2022 (令和5) | 問題・解答(PDF) |
| 2021 (令和4) | 問題・解答(PDF) |
▼教職教養の概要や出題傾向を以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい

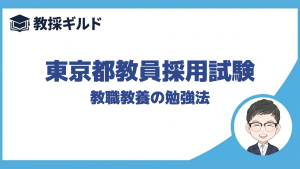
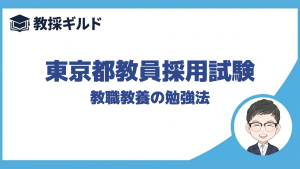
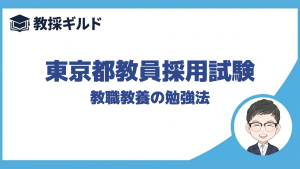
【東京都教員採用試験】教職教養の勉強法|出題傾向と優先順位
「東京都の教員になりたいけど、教職教養の科目が多すぎて何からやればいいかわからない……」 もし、「とりあえず全科目、参考書の最初から勉強しよう」と考えているなら…
専門教養の問題・解答(過去5年分)
小学校
中学校
中高共通
小中共通
- 理科:令和5年度以前は小学校(理科コース)で募集
小中高共通
- 保体:令和5年度以前は中高共通で募集
高等学校
- 商業:令和4年度は募集なし。
- 水産:令和4年度は募集なし。
特別支援学校
| 教科 | R8 | R7 | R6 | R5 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 社会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数学 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 理科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音楽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家庭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英語 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自活 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 理療 | ○ | ○ | ○ | – | – |
- 理療:令和5年度以前は募集なし。
養護教諭
▼専門教養の概要や特色を以下の記事でまとめています。
あわせて読みたい

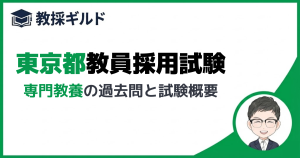
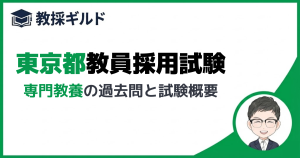
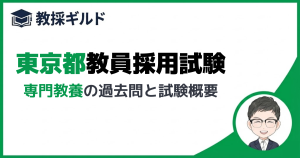
【東京都教員採用試験】専門教養の傾向と試験概要まとめ
東京都教員採用試験の専門教養は、志望する校種・教科の専門知識が問われる重要な試験です。 この記事では、専門教養の試験概要と対策方法をまとめています。 福永です…
【東京都教員採用試験】過去問を使った効果的な活用法
過去問データをダウンロードして満足していませんか?
多くの受験生が次のような使い方をしてしまいます。
- 1年分を解く
- 点数を見て一喜一憂する
- 解説を読んで終わり
この方法では、自分の実力を確認できるだけで、本番で点数を伸ばすことはできません。
過去問は「解く前」に使う
合格する人は、過去問を解く前に分析します。
具体的には、次の3ステップで進めます。
- 分析する:東京都で毎年出る分野と、ほとんど出ない分野を確認する
- 計画を立てる:出ない分野の勉強時間を減らし、頻出分野に時間をかける
- 演習する:東京都の出題傾向を理解したら、他の自治体の似た問題で練習する
この方法で勉強すると、無駄な勉強を減らせて、300時間ほど短縮できる可能性があります。
「具体的にどうやって分析すればいいの?」「他の自治体の問題はどう選べばいいの?」と思った方は、以下の記事をご覧ください。
あわせて読みたい

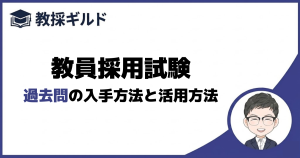
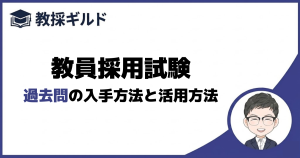
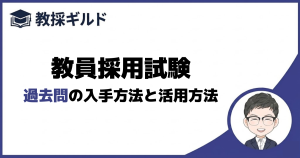
【全自治体一覧】教員採用試験の過去問の入手方法と活用法
教員採用試験に合格するには、過去問の分析が欠かせません。 「どの自治体が公開しているの?」「どうやって手に入れるの?」 そんな疑問を持ってこのページにたどり着…



合格者が実践している過去問分析の3ステップを、図を使ってわかりやすく説明しています。
【東京都教員採用試験】過去問まとめ
今回は、東京都教員採用試験の過去問と活用方法を紹介しました。
過去問を解くと、次の2つがわかります。
- 今の実力と合格ラインの差
- よく出る分野
過去問を使うときは、目的を決めてから取り組みましょう。
過去問を使う目的の例
- 今の実力を確認する
- 出題傾向を分析する
- 全体の復習をする
目的を決めてから過去問を使えば、限られた時間を無駄にせず、効率的に合格に近づけます。