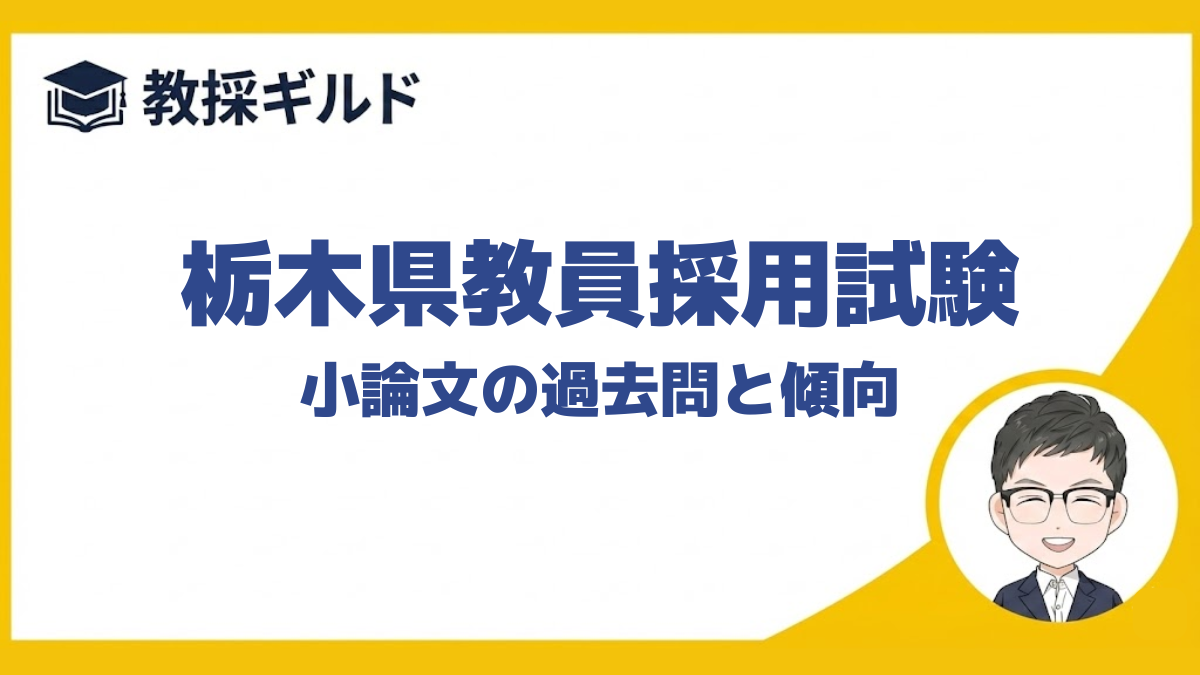栃木県教員採用試験の二次試験では、試験時間50分で800字程度を書く小論文が実施されます。
試験時間や文字数、評価基準を知らずに対策を始めてしまうと、的外れな準備になる恐れがあります。
この記事では、小論文対策を始める前に押さえておきたい以下の情報をまとめました。
- 試験時間・文字数
- 配点・評価基準
- 過去の出題テーマ・合格の型
試験の全体像を正しく理解し、合格に向けた方向性を整理するための資料としてご活用ください。
小論文の試験内容
栃木県教員採用試験の小論文は、第二次選考で行われます。
対象校種は、高校・特別支援学校・養護教諭です。
小論文の試験概要
まずは、試験の全体像を紹介します。
| 対象教科 | 高校、特別支援学校、養護教諭 |
|---|---|
| 試験時間 | 50分 |
| 文字数 | 600字~1000字 |
| 問題数 | 1題 |
試験時間50分に対して、文字数は600字から1000字と制限があります。
- 文字数は何文字書けばいいの?
-
8割程度は書くことを推奨します。
600字を超えれば評価はされますが、600〜700字では、文字数の評価は高くならないはずです。
他自治体でも文字数の加減では評価になっていない場合もあるため、8割程度を目指して練習しましょう。
小論文の評価基準・配点
小論文は次の3つの観点に沿って評価されます。
- 内容
- 文章構成
- 文章表現力
最終的にA~Cの三段階で採点されます。



C評価は足切り(不合格)になるので注意してください!
小論文の過去問(テーマ)
過去に出題された過去問(テーマ)を紹介します。
令和7年度(2024年実施)*共通
「第4期教育振興基本計画」(令和5年6月16日閣議決定)では、計画のコンセプトに、日本社会に根差したウェルビーイングの向上をあげている。ウェルビーイングを構成する要素の一つとして自己肯定感があるが、日本の子供は諸外国の子供に比べて自己肯定感が低いという調査結果がある。あなたは、教師として子供たちの自己肯定感を高めるためにどのような取組をしていこうと考えるか。具体的に書きなさい。
※ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含むものである。また、個人のみならず、個人を取り巻く場や地域、社会が持続的に良い状態であることを含む包括的な概念である。(出典:文部科学省「第4期教育振興基本計画」)
令和6年度(2023年実施)
| 高等学校 | 令和3年1月中教審答申では、「令和の日本型学校教育」を担う教職員の姿の一つとして、「子供一人一人の学びを最大限に引き出し、主体的な学びを支援する伴走者としての役割を果たしている」ことが示されています。そこで、主体的な学びを支援するために、あなたが教員として勤務する上で、自身の教員としての「強み」を学校現場にどのような場面で、どのように生かしていきたいか、自身の「強み」を明確にしながら具体的に書きなさい。 |
|---|---|
| 特別支援 | |
| 養護教諭 | 令和5(2023)年6月に閣議決定された教育振興基本計画では、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」が示されている。そこで、あなたは、児童生徒が相互に多様性を認め、高め合う心を育むために、具体的にどのような取組をしていきたいか、理由を含めて書きなさい。 |
令和5年度(2022年実施)*共通
「栃木県教育振興基本計画2025-とちぎ教育ビジョン-」では、「とちぎに愛情と誇りをもち 未来を描き ともに切り拓くことのできる 心豊かで たくましい人を育てます」を基本理念としています。あなたが考える「心豊かで たくましい人」とはどのような力を持った人か。また、その力を児童生徒に身につけさせるため、教員としてどのような取組をしていこうと考えるか書きなさい。
令和4年度(2021年実施)*共通
児童生徒がよりよく自己実現を図っていくためには、社会との相互関係を保ちつつ、自分の未来を創る力を育むことが重要である。あなたの考える「自分の未来を創る力」とは何か。また、その力を身につけさせるためにどのような取組をしていこうと考えるか書きなさい。
令和3年度(2020年実施)*共通
とちぎの求める教師像では、「確かな指導力」が掲げられているが、あなたが考える「指導力」とは何か。また、その「指導力」をどのように身に付けていきたいか、書きなさい。
令和2年度(2019年実施)*共通
社会の進歩や変化が急激に進む中、今の子供たちには、予測困難な社会を生き抜いていく力が必要とされている。このような力を子供たちに身に付けさせるために必要な教員の資質能力とは何か、また、その資質能力を身に付けるためにどのような取組をしていくか、具体的に書きなさい。
合格答案の「型」と書き方(模範解答)
論作文で高得点を取るには、採点官が読みやすい「型」に当てはめて書くことが鉄則です。
合格する論作文の多くは、以下の構成を基本として書かれています。
- 序論(10%):現状の課題 + 栃木県の教育目標 + 取り組む決意
- 本論(80%):必要な資質能力 + 具体的な取組① + 具体的な取組②
- 結論(10%):まとめ + 「とちぎの求める教師像」への展望
では、この「型」を使うと評価がどう変わるのか。
実際のテーマを例に、NG例とOK例を比較してみましょう。
社会の進歩や変化が急激に進む中、今の子供たちには、予測困難な社会を生き抜いていく力が必要とされている。このような力を子供たちに身に付けさせるために必要な教員の資質能力とは何か、また、その資質能力を身に付けるためにどのような取組をしていくか、具体的に書きなさい。
【NG】評価されない書き出し
多くの受験生が書いてしまうのが、文体は合っていても中身が「感想文」になっているパターンです。
今の社会は変化が激しく、子供たちが生きていくのは大変な時代だと思う。だからこそ、教師は子供たちに寄り添い、どんな困難にも負けない強い心を育てなければならない。そのために必要なのは、教師自身が情熱を持ち、諦めずに指導する力だ。私は、子供たちの手本となれるよう、日々全力で勉強し、子供と一緒に成長できる教師になりたい。
「〜だと思う」「強い心」という主観的な表現になっています。
また、栃木県が重視する「教育振興基本計画」や「育成指標」の言葉が全く示されていません。「全力で勉強」では、具体的な手段が不明確です。
【OK】評価される書き出し
次に、先ほどの「型」に当てはめた合格レベルの文章です。
現在は予測困難な時代と言われており、子供たちには、変化を前向きに捉え、他者と協働して課題を解決する力が求められている。栃木県教育振興基本計画においても、基本理念として「心豊かでたくましい人を育てます」と掲げられている。このような子供たちを育てるために、教員には社会の変化に対応できる「幅広い視野」と、子供の可能性を引き出す「確かな指導力」が必要であると考える。私はこれらの資質能力を身に付けるため、以下の二点の取組を行う。
個人の感情ではなく、栃木県教育振興基本計画の理念や「とちぎの求める教師像」のキーワードを用いて、論理的に書かれています。



ただし、この書き出しはあくまで「宣言」に過ぎません。合格するためには、この後に続く本論で「研修や協働による具体的な実践」を提示する必要があります。
余談ですが…、「以下の二点の実践に取り組む」と宣言したあと、
あなたは自信を持って「採点官を納得させる具体策」を書けますか?
ここがフワッとした精神論になってしまい、
点数を落としてしまうケースが本当に多いです。
以下のnoteでは
過去5年分の「模範解答(全文)」と、
あなたの答案を直接チェックする「個別指導・添削サポート」を実施中です。
「埋めることはできるけど、正解が分からない」
そんなモヤモヤがある方は、答え合わせに使ってください。
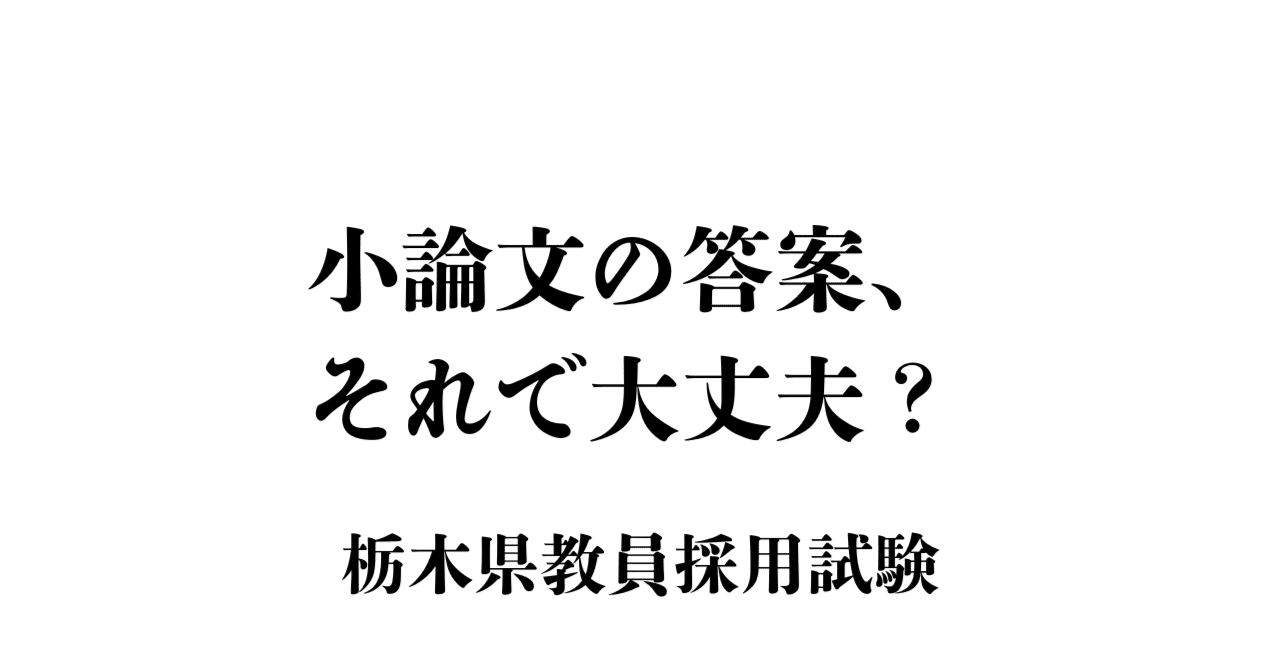
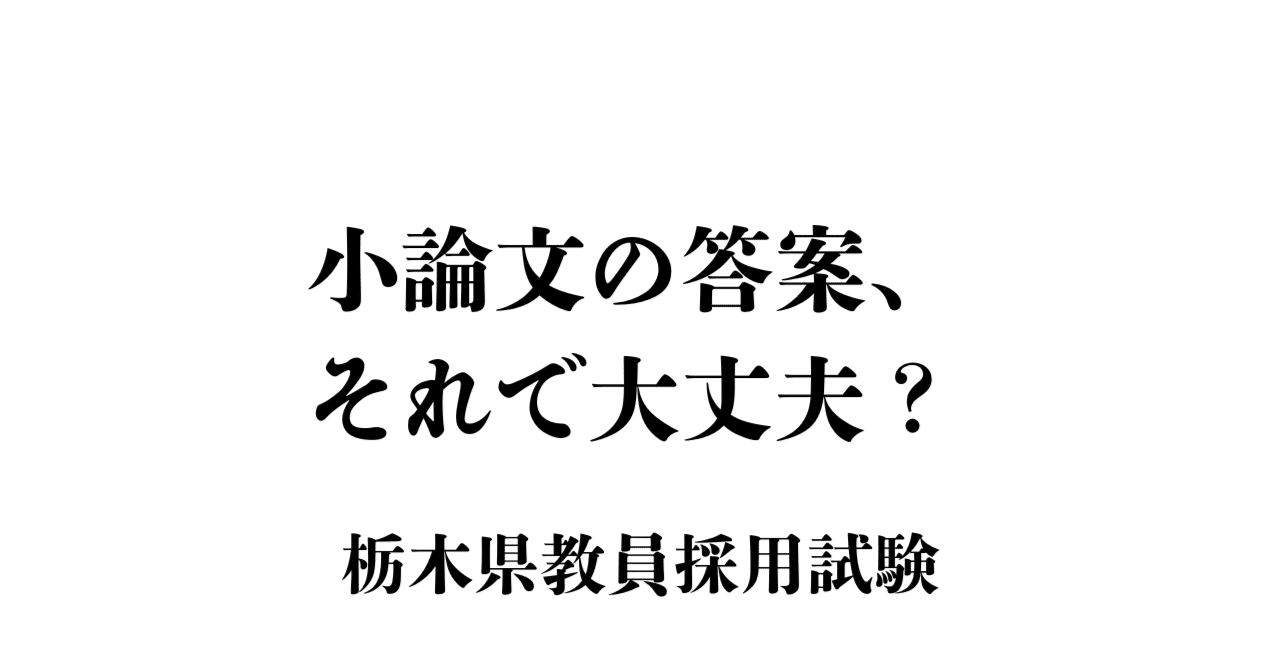
小論文まとめ
今回は、栃木県教員採用試験における小論文の傾向と過去のテーマをまとめていました。
小論文の対策は、やるべきことが想像しているよりも多いです。
過去問を眺めるだけでは、小論文を攻略することはできません。過去問を使って答案を作成し、その上で添削を受けることで徐々に上達します。
小論文で落ちる人ほど、書いたら書きっぱなしってことが多いです。答案を書いて誰にも見せないというのは、問題を解いても答え合わせをしないのと同じなので注意しましょう。
で、ここからどうするか。
過去5年分の全文解答と、回数無制限の個別添削が受けられるnoteを用意しました。「これで合ってる?」が全部クリアになります。
文字数配分、構成の作り方、評価される表現。合格答案を書くための技術を解説した記事から始めましょう。
倍率や試験日程、面接などの記事もあります。気になるところから読んでみてください。



今日のうちから1つ行動してみましょう!