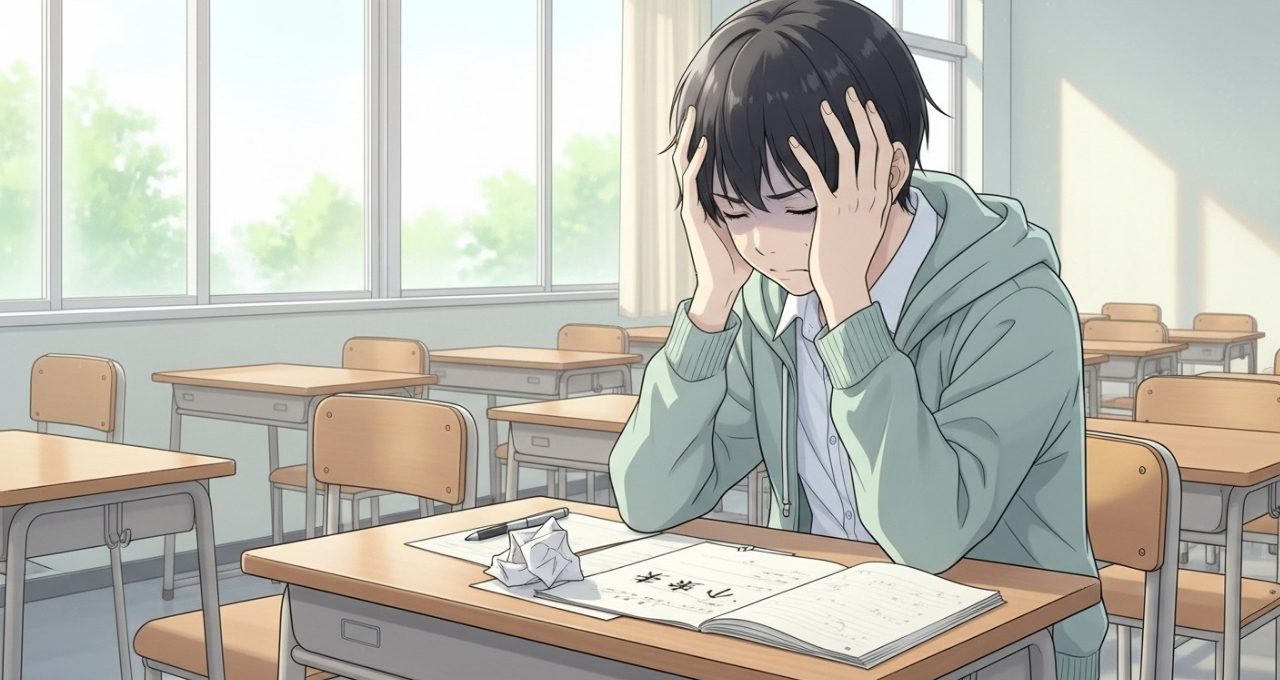山口県教員採用試験(通称:山口県教採)の小論文について解説します。
- 小論文ってどんな試験なんだろう…。
- どんなテーマが出ているの?
- なにを書いたら合格できるの?
このような悩みや不安をお持ちなのではないでしょうか。
山口県教採の小論文は、ただテーマに沿って文章をダラダラ書くだけでは評価されないのです。
正しい型や評価ポイントを知らずに対策しても、合格は勝ち取れません。
そこで本記事では、山口県教員採用試験の小論文について以下の3点を解説します。
- 小論文の概要(試験時間、文字数、評価基準)
- 過去5年分の出題テーマ
- 評価を落とす・評価される模範解答例
この記事に書かれていることを実践すれば、あなたの面接への不安は自信に変わりますよ。
【山口県教採】小論文試験とは?
山口県教員採用試験の小論文は第2次試験で実施されます。
筆記試験では判断できない、論理的思考力や読解力、教師としての適性などを総合的に評価します。
概要(試験時間・文字数)
まずは、試験時間や文字数などの概要を把握しましょう。
- 試験時間:50分間
- 文字数:800字以内
試験時間のわりに、文字数が多いです。
目安として700字は書けるように練習してください。
評価基準
小論文は以下の評価基準で採点されます。
- 教育的愛情
- 教育に対する情熱・意欲
- 教育観
- 人権意識
- 倫理観
- 表現力
- 創造力
- 指導力
- 社会性
- 積極性
- 協調性等
最終的にA~Eの5段階で総合評価をつけます。
D評価以下で不合格になるので注意が必要です。
【山口県教採】小論文の過去問(テーマ)
ここでは、山口県教員採用試験の小論文の過去問(テーマ)を紹介します。
出題傾向を把握し、どのようなテーマが重視されているのかを確認しましょう。
令和7年度(2024年実施)
子どもたちの教育を担う教員は,自身の専門教科等に関わる専門性はもとより,豊かな人間性や社会性が必要であり,教職生涯を通じて学び続けることが求められています。あなたは,なぜ,教員自身が学び続けることが求められていると考えますか。また,あなたは,教員としてどのような姿をめざし,どのように学びを深めていきますか。具体的に書いてください。
令和6年度(2023年実施)
今日、いじめをはじめとして生徒指導上の課題が複雑化する中、課題を抱えている特定の児童生徒への指導・援助だけでなく、全ての児童生徒の発達を支える生徒指導も重要とされています。あんたは、なえ、このような生徒指導が重要だと考えますか。また、あなたは教員として、日常的な教育活動の中で、どのようなことに気をつけながら生徒指導に取り組んでいきますか。具体的に書いてください。
令和5年度(2022年実施)
急激に変化する時代の中で、学校教育においては全ての子どもたちの可能性を引き出す、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現が求められています。あなたは、なぜ、この実現が求められていると考えますか。また、あなたは教員として、その実現に向けて、どのようなことに取り組んでいきますか。具体的に書いてください。
令和4年度(2021年実施)
山口県では、学校・家庭・地域が連携・協働した教育を推進しています。あなたは、なぜ、現在、このような教育が必要だと考えますか。また、あなたは教員として、家庭・地域と一体となって、どのような教育活動に取り組んでいきますか。子どもたちに育みたい能力や態度等を踏まえて、具体的に書いてください。
令和3年度(2020年実施)
「Society5.0」といわれる超スマート社会の到来、グローバル化の加速など、これからの複雑で予測困難な時代を迎えるにあたって、児童生徒が主体的に自らの未来を切り拓いていくために、どのような力を育成することが求められると、あなたは考えますか。また、あなたは教員として、児童生徒が主体的に自らの未来を切り拓いていくための力を育成するために、どのように取り組んでいきますか。具体的に書いてください。
▼もっと過去のテーマを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【山口県教採】小論文の模範解答例
では、実際にどんな答案を書ければ評価をもらえるのか。逆に、どんな論文だと不合格になるのかを解説します。
問題
子どもたちの教育を担う教員は,自身の専門教科等に関わる専門性はもとより,豊かな人間性や社会性が必要であり,教職生涯を通じて学び続けることが求められています。あなたは,なぜ,教員自身が学び続けることが求められていると考えますか。また,あなたは,教員としてどのような姿をめざし,どのように学びを深めていきますか。具体的に書いてください。
令和7年度(2024年実施)テーマより
解答例
グローバル化や高度情報化など、現代社会は急激に変化しており、子どもたちを取り巻く環境も複雑化している。①このような時代において、子どもたちが未来を生き抜く力を育むためには、その指導者である教員自身が絶えず学び続けることが重要だと私は思います。
②私が目指す教員像は、子どもたち一人ひとりの心に寄り添い、その可能性を最大限に引き出すことができる教員です。また、学習指導だけでなく、豊かな人間性を育む指導も行い、保護者や地域社会からも信頼される存在になりたいです。
その実現のため、私は資質能力の向上に多角的に取り組んでいきます。③まず、専門性を高めるために、主体的・対話的で深い学びを実現するための研修会に積極的に参加し、最新の指導法を学びたいです。ICT活用スキルも必須であるため、実践的な研修も受講したいです。次に、豊かな人間性を育むために、教育関連の書籍だけでなく、幅広い分野の読書を通して見識を広めようと思います。④また、現場に出てからは、先輩の先生方の優れた実践から謙虚に学び、同僚性を大切にしながら指導力を高めていきたいと考えています。⑤コミュニケーション能力も、子どもたちや保護者と良好な関係を築く上で非常に重要なので、日々の関わりの中で磨いていきたいです。⑥教員の学びは、全て子どもたちの成長に還元されるべきものです。
私は、山口県の教育に貢献できるよう、常に自己研鑽に励み、子どもたちと共に成長し続ける教員を目指して、日々努力していきたいです。
この解答例は、一見すると構成が整っており、キーワードも盛り込まれているため、それなりに書けているように見えます。
しかし、多くの減点ポイントを含んでおり、合格点を得ることは極めて難しいでしょう。
当たり前のことを述べているだけで、独自の視点がない。また、「~と思います」という表現は、自信のなさと他人事のような印象を与えます。
小論文は、あなたの意見を明確に主張する場です。「~と考える」「~である」と断定的に書きましょう。
のように、独自の教育観を示すと序論から差がつきます。
非常に抽象的です。
「心に寄り添う」「可能性を引き出す」「信頼される」は、誰もが言う理想像であり、あなたがどのような教員になりたいのか、その人物像が全く見えてきません。
これでは、評価項目にある「教育観」や「創造力」をアピールできません。あなた自身の経験に基づいた、より具体的な教員像を示すべきです。
のように、背景が見える言葉で語ることが重要です。
最も大きな問題点です。「何を学ぶか」が、ただの行動リストの羅列になっています。
「研修に参加する」「読書をする」といった行動は誰にでも書けます。しかし、評価者が知りたいのは「なぜ、何を学び、それを子どもたちにどう還元するのか」という思考の過程です。
これでは「指導力」や「積極性」が伝わりません。
複数の取り組みを浅く並べるのではなく、一つか二つに絞り、深く掘り下げましょう。
まで具体的に記述する必要があります。
「~したいと考えています」という願望の表現は、主体的な決意や意欲を弱めてしまいます。
教員になるという強い意志を示す場なので、受け身な姿勢ではなく、自ら行動する積極性を示すべきです。
「~していく」「~する」という決意の言葉を使いましょう。
のように、具体的な行動を伴う表現にすることが重要です。
論理的なつながりが弱く、思いつきで付け足したような印象を与えます。
前の文脈との関連性が薄く、文章全体の一貫性を損なっています。
この要素を入れたいのであれば、例えば、
のように、全体の文脈の中に位置づける工夫が必要です。
精神論だけで終わっており、具体性がありません。
本論で述べたことを自分の言葉で力強く再確認し、教職への熱意を示すべき場面で、「努力します」という言葉だけでは想いは伝わりません。
本論で述べた自身の具体的な取り組みと結びつけ、
のように、力強い決意表明で締めくくりましょう。
模範解答例(タップして表示)
予測困難な時代を生きる子どもたちの教育を担う教員には、専門性と共に豊かな人間性が求められ、常に学び続ける姿勢が不可欠である。私が、教員は学び続けることが求められると考える理由は、第一に、変化の激しい社会に対応する力を子どもたちと共にはぐくむためであり、第二に、多様化する子どもたち一人ひとりに深く寄り添うためである。
私は、子どもたちの「なぜ」という探究心に火をつけ、その学びに寄り添いながら自らも成長し続けられる教員を目指す。単に知識を教え込むのではなく、子どもたちが自ら課題を発見し、他者と協働しながら解決していく学びの伴走者となりたい。
その実現のため、まず専門性の深化に努める。大学で学んでいる専門教科の知識はもちろんのこと、GIGAスクール構想に対応できるICT活用指導力を高めたい。教育実習において、デジタル教材を活用した際の生徒たちの生き生きとした表情が忘れられない。県の総合教育センターが実施する研修等にも積極的に参加し、子どもたちの知的好奇心を刺激する授業実践力を磨いていく。
次に、豊かな人間性をはぐくむために、多様な価値観に触れる学びを深める。教育実習でおとなしい生徒が、休み時間には驚くほど熱心に地域の伝統文化について語ってくれた経験から、生徒理解の多角的な視点の重要性を学んだ。教員になったら、地域の行事やボランティア活動に参加し、保護者や地域の方々と積極的に対話し、そこから得た学びを教育活動に還元することで、子どもたちの豊かな人間性を育んでいきたい。
山口県の子どもたちが、自らの可能性を信じ、未来を切り拓く力を身に付けられるよう、私自身が学びの主体であり続け、謙虚な姿勢で探究し続けていきたい。
▼他年度の模範解答例も作成しています。以下の記事をご覧ください。
まとめ|【山口県教採】小論文で落ちないために
今回は、山口県教員採用試験における小論文の傾向と過去のテーマを紹介してきました。
教採の小論文対策は、想像しているよりもやるべきことが多く、過去問を眺めるだけでは攻略できません。実際に書いてみて、課題に気づき、改善を繰り返すことで力がついていきます。
大切なのは、過去問を使って答案を書き、それを誰かに添削してもらうことです。自分では気づけない文章のクセや論理の弱さを客観的に知ることが、合格に近づく第一歩です。
小論文で不合格になる受験者の多くは、「書いたら書きっぱなし」で終わってしまっています。答案を書いて誰にも見せないのは、問題を解いても答え合わせをしないのと同じです。それでは上達しません。
小論文が原因で不合格にならないよう、早めに対策を始めましょう。遅くとも試験の3ヶ月前には、答案作成と添削を含めた本格的な準備を始めるのが理想です。
以上、山口県教員採用試験の小論文対策についてのまとめでした。過去問を活用しながら、実践的なトレーニングを重ねていきましょう。
もし一人での対策に困ったり、不安を感じたりしたときは、遠慮なく僕を頼ってほしいです。あなたが合格できるよう、全力でサポートします!
▼小論文の個別コーチングは以下の記事をご覧ください。